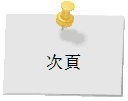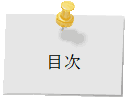映画の原題である。この原題が2001年を象徴しているような気がしたのと、邦訳「耳に残るは君の歌声」も面白い訳かなと思い見に行った。
はたせるかな予想に違わぬいい映画で、今年を締めくくるにふさわしい出来映えであった。サリー・ポッターが脚本、音楽を担当し、監督まで兼ねているのは、よほどこの作品に賭けるものがあってのことだと思われる。彼女の言を借りれば、「20世紀には泣きたいことがたくさんあった」のであり、それはまさに言い得て妙なのである。
もっとも、泣きたいことがたくさんあるのは何も20世紀に限ったことではなく、そんな事は誰でも承知しているわけで、ただ、同時代人として20世紀はたしかに残酷な世紀であったと思うのである。
さて、この「THE MAN WHO CRIED」は反語である、そして同時に現実の内なる叫びである。叫び声をあげたくてもあげれない人々、沈黙せざるをえない多くの人々を意識してつくられた作品である。しかし単にそれだけなら新聞、テレビが毎日のように正義漢面して大いに偽善者ぶりを発揮している、われわれが沈黙者の代弁をしているのでございますという傲慢さで。
映画がテレビ、新聞と一線を画しているのは、いまさら声高に言うような事ではないが、一言でいうなら芸術性であろう。テレビや新聞は、前線で戦っている報道人を除き、デスクでタバコをくゆらせながら爆死した人々を報じたり談じたりしているのである。タバコの箱をあけるのと同じような感覚で前線で路頭に迷う人々の生活を開いて、一体何が読みとれるというのか。人の心の奥深さが読みとれるとでも思っているのであろうか。
前線で戦っている報道陣とは、たとえばNHKの二村伸。彼は常にきな臭い戦場の最前線にいる。二村伸のいのちは24時間ずっと危険にさらされていて、この12年間よくもまあ殉職の憂き目にあわなかったことかと不思議なくらいである。湾岸戦争〜コソボ〜アフガンに至るまで、彼はいつも戦場にいた。テレビに出てきた二村伸の顔を見るたびに私はホッとする。やれやれまだ生きていてくれたと。
事と次第は異なるが、マスードがテレビに再び登場してきたのは死んだ後のことであったから、いっそう不安なのである。マスードは二村伸以上に死と隣り合わせであったのだが。
さて、映画の話に戻ることにしよう。サリー・ポッターがほかのメディア人間と違うのは、彼女が芸術を志向しているからであり、芸術とはわれわれ人間を根元的な闇から連れだすものである事を認識しているからである。過去でも現在でも、芸術活動はわれわれを闇から連れ戻すよすがとして続けられてきたのだ。
この映画は子役が印象的である。印象的というといかにも月並みだが、「太陽の帝国」の子役クリスチャン・ベール以来の名子役といっていいように思う。勿論、名子役は他にもいる。「マルセルのお城」のマルセルとリリを見て、私は南仏に旅したばかりか、「幻想都市」という長い文章まで書く気になった。映画はだから怖い。
私は映画評論をなりわいとしているわけのものではないので人に薦めはしない。わずか数点ではあるが、今年もいい映画に恵まれた。父子の絆の尊さにこころ打たれた。愛し合う者が引き裂かれるかなしさは言葉で言い表せるものではない。「真珠採り」の歌がその悲哀をあらわしているのだが、大昔、リカルド・サントスの「真珠採りのタンゴ」は父の好きな曲のひとつであった。父は48歳で鬼籍に入ったが、私は父より長く生き恥をさらしている。
|